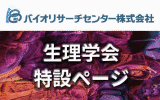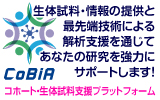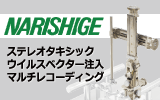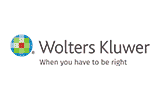プログラム
公募シンポジウム
1. ポリアミンの多彩な生理機能
Pleiotropic functions of polyamines
日時 3月28日(日)9:00~11:00
ポリアミンはあらゆる生物の細胞内に存在する小さな有機分子であり、その陽イオン性によって核酸、リン脂質、タンパク質などに結合して細胞の増殖や分化を始めとする多様な細胞機能に関与している。ポリアミンに関する研究はこれまでの抗がん剤を目指すものから、神経変性疾患、アンチエイジングなどへと広がりを見せている。本シンポジウムでは特に生理機能に関連する話題としてKurata(カナダ)は内向き整流性カリウムチャネル機能のポリアミンによる制御、大城戸は呼吸機能におけるポリアミンの作用と治療への応用、日浅は小胞型ポリアミン輸送体VPATの局在と生理機能、山澤は骨格筋の増殖・分化におけるポリアミンの作用について議論することを通して、今後の生理機能に関連するポリアミン研究の可能性を討論する場としたい。
座長:
柳(石原) 圭子
(久留米大学)
大城戸 真喜子
(東京慈恵会医科大学)
2. 倹約型表現型を形態と機能から統合的理解する
Comprehensive understanding of the shape and function of “The Thrifty Phenotype”
日時 3月28日(日)9:00~11:00
胎生期の栄養不良は、脳重量を守るために代謝・内分泌系を変化させるトレードオフを行うことで倹約型表現型を獲得する。”Predictive Adaptive Responses (PARs) 仮説“として認知されるこの表現型の変化は、生後の環境が栄養不良であれば保護の形となるが、富栄養環境に曝されると栄養過多となり肥満や耐糖能異常などの種々の代謝性疾患のみならず心血管疾患や精神神経疾患を含む非感染性慢性疾患の発症リスクとなる。しかしながら、PARsを誘導する機序の詳細は不明な点が多く、トレードオフにより生じる脳保護作用や代謝・内分泌系変化の全体像は把握できていない。そこで、本シンポジウムでは低栄養による身体変化の研究に携わる研究者と共に形態と機能からトレードオフとPARs仮説を考察し、倹約型表現型とは何かを統合的に理解したい。本シンポジウムでは若手研究者の発表を広く公募し、歓迎する。
座長:
根本 崇宏
(日本医科大学)
内村 康寛
(滋賀医科大学)
3. 損傷脳に対する細胞移植治療とリハビリテーション医療の可能性
The potential of stem cell and rehabilitation therapies for brain disorders
日時 3月28日(日)14:20~16:20
成熟哺乳類の中枢神経系に一度損傷が起きると、再生・修復が不可能とされてきた。近年、目まぐるしい再生医療研究の発展により、これまで治療が困難とされてきた中枢神経疾患が、動物実験や臨床試験を通して有効性が証明されるようになってきた。中でも、細胞移植治療は、失われた細胞を外部から補充することにより、失われた機能を再獲得するための治療法として大いに期待されている。当初、再生医療は、後遺症を残さない根治療法を目指した新規治療法として考えられてきたが、世界中で臨床試験が進むにつれ、細胞移植治療だけでなく、ホスト側の神経賦活化法としてリハビリの重要性が認識されてきている。本公募シンポジウムでは、損傷脳に対する細胞治療やリハビリ領域に精通する基礎及び臨床のスペシャリストの先生方をお招きして、細胞移植治療やリハビリを利用した脳障害の機能再生・再建の可能性について議論していきたい次第である。
座長:
田尻 直輝
(名古屋市立大学)
出澤 真理
(東北大学)
4. 循環のフィジオーム
Physiome of the Circulation
日時 3月28日(日)14:20~16:20
階層的な生体機能を系統的・網羅的に解析し、実験と理論研究を通じて生体機能をシステムとして理解する研究をフィジオーム研究という。フィジオーム研究が強みを発揮できる生体の機能として、血液循環を司る心血管腎臓の機能がある。この系では、細胞レベルから臓器レベルの多階層に渡り、幾重のフィードバック機構によって制御され、その頑健性が維持されていると考えられるが、本質的な理解は未だ得られていない。本シンポジウムは、日本生理学会フィジオーム委員会メンバーによって企画した。最新の研究成果を各研究者から説明頂き、血液循環の制御機構を中心議題として、フィジオーム研究の重要性や今後への期待を議論する。特に、そのフィードバック機構で見られる、形態・解剖学的な特徴と生理機能の連関について議論し、生理学会員のみならず、解剖学会員にも重要な知見を与える。そして、我が国におけるフィジオーム研究の奨励を大きな目的としている。
座長:
倉智 嘉久
(大阪大学)
八木 哲也
(大阪大学)
5. 呼吸中枢の解剖と生理:呼吸のリズム形成と低酸素応答機構研究の新展開
Anatomy and physiology of the respiratory center: cutting-edge research on the mechanisms of respiratory rhythm generation and hypoxic responsiveness
日時 3月28日(日)14:20~16:20
生体は常に体内の酸素化状態をモニターしつつ1回毎の呼吸出力を調節している。この呼吸リズム形成と酸素レベルの恒常性維持機構は、これまで詳細な解明がなされていなかったが、近年の研究の進歩により、呼吸リズム形成では延髄傍顔面神経核呼吸ニューロン群および延髄PreBotzinger Complexの神経回路網の重要性が明らかにされてきた。また、低酸素呼吸応答機構では末梢化学受容体の他、脳幹部のニューロンとアストロサイトが低酸素センサー細胞として働いていることが明らかにされてきた。さらに低酸素感受の分子メカニズムとして低酸素感受性イオンチャネルTRPA1の重要性も解明されてきた。本シンポジウムでは、これら呼吸リズム形成および低酸素呼吸応答に関する最先端の研究成果を持ち寄り討論を行う。その成果は、睡眠呼吸障害などの呼吸調節障害や様々な呼吸器疾患に伴う低酸素病態のより適確な理解に寄与すると期待される。
座長:
岡田 泰昌
(村山医療センター)
池田 啓子
(村山医療センター)
6. 部分と全体学で中枢神経系の構造-機能連関の解明に挑む
Mereological approach for unraveling the structure-function relationship of the central nervous system
日時 3月28日(日)14:20~16:20
生体の中でも環境や他者とのコミュニケーションを司る脳・神経系は、生体システムの中でも際立って複雑な階層構造を持つことに加えて、階層間で情報の発散と収束が行われている。つまり、脳・神経系は構造的な階層構造に加えて、情報という機能的な階層構造をも持つ。そのため、ある一部の細胞などの「部分」の機能と構造を精密に計測しても脳の機能解明を行うことはできないし、逆に、脳あるいは生体「全体」の入力と表現型との関係を精密に計測しても、脳はブラックボックスのままである。脳・神経系は部分と全体が相互に作用して機能発現をしているため、その機能を解明するためには「部分と全体」の問題 (mereology) を双方向的に解明する必要がある。そのためには、単一計測モダリティに囚われない、マルチモーダル・マルチスケール計測・解析技術が必要である。そこで本シンポジウムでは電気・光・磁気・数理を駆使して「部分と全体」問題の解決を目指している研究者に講演頂き、脳と生体のメレオロジーについて議論する。
座長:
小山内 実
(大阪大学)
虫明 元
(東北大学)
7. オリゴデンドロサイト研究の新展開
New insight into oligodendrocyte research
日時 3月28日(日)14:20~16:20
中枢神経系のオリゴデンドロサイトはニューロンに髄鞘(ミエリン)を形成することにより、活動電位の伝導速度を飛躍的に上昇させている。従来、ミエリンは神経軸索を取り巻く単なる鞘と認識されていたが、ニューロンと相互作用することにより脳の高次機能を調節する新たな作用が知られてきている。また、オリゴデンドロサイト異常によりミエリンが脱落すると脱髄性疾患が引き起されるが、さらに統合失調症などの精神疾患にオリゴデンドロサイトが関与することも分かってきている。 当該公募シンポジウムでは、3D電顕や、電気生理、新規イメージング技術等を用いてオリゴデンドロサイト研究において活躍されている先生方に御口演いただき、「more than sheath」であることが分かってきた新しいミエリン機能と、その異常に起因する神経疾患について理解を深めていきたい。
座長:
清水 健史
(名古屋市立大学)
板東 良雄
(秋田大学)
8. 心臓循環系疾患とその修正可能及び不可避な危険因子に関するクロストーク:体循環及び脳循環動態やその調節機能について
Crosstalk in modifiable and non-modifiable risk factors for cardiovascular disease
日時 3月28日(日)16:30~18:30
高血圧などの生活習慣病は、心血管疾患、糖尿病、動脈硬化、うっ血性心不全や脳血管疾患などの心臓循環系疾患発症リスクである。しかしながら、生活習慣病は、遺伝的要因、例えば年齢、性別、人種、加齢、家族病歴などの変更不可避の危険因子と異なり、適切な生活習慣、例えば、適切な食習慣や体重コントロール、習慣的な運動などライフスタイルの見直しにより改善可能である。一方、この変更可能要因(生活習慣病に関連する運動や食習慣等)及び変更不可要因(加齢、性別、人種等)は、体循環や脳循環調節機能やその動態に複雑に影響を及ぼすため、これらの要因がどの様に心臓循環系疾患発症に関連するか十分に明らかにされているとは言えない。本シンポジウムでは、心臓循環系疾患発症に対する変更可能および変更不可能な危険因子に焦点をあて、脳及び体循環動態またその調節機能への影響について議論する。
座長:
小河 繁彦
(東洋大学)
9. 生殖生物学の新展開
Reproductive biology up to date
日時 3月28日(日)16:30~18:30
本シンポジウムは、生殖生物学領域における幅広い生命現象を対象にして、先鋭的な研究を展開している6名の研究者により構成される。始原生殖細胞から生殖細胞が形成される過程でのエピゲノムリプログラミング、体細胞分裂から減数分裂への切り替え機構、ライディッヒ細胞の分化機構、生殖器毒性と精巣毒性、神経伝達物質による受精調節に関する最新の研究成果を発表していただき、聴衆の皆様と議論を深める場としたい。
座長:
若山 友彦
(熊本大学)
藤ノ木 政勝
(獨協医科大学)
10. 核膜バイオロジー-核膜構造/機能と老化・疾患
Nuclear envelope biology - the structure and function of nuclear envelope, aging and disease caused by its abnormalities
日時 3月28日(日)16:30~18:30
核膜は、2枚の脂質二重膜(内膜および外膜)、核膜孔、そして核ラミナの3つのコンポーネントから構成されている。染色体の格納場所として細胞質と境界を形成する役割に加え、核膜孔を介する選択的な物質輸送、染色体構造の制御、遺伝子転写調節など多彩な機能を備えている。細胞の老化や種々の細胞ストレスは、核膜構成因子の品質劣化や変性を起こし、核輸送破綻や核膜崩壊など重篤な核機能障害を誘発する。これらの現象が筋ジストロフィーなどの核膜病や個体の老化現象に密接に関連することから、核膜の多機能構造とその破綻の分子機構に注目が集まる。本シンポジウムでは核膜研究の最前線で新たな局面を切り拓いた研究者に、核膜構造/機能の基礎から老化・疾患発症に至るまで最新のトピックスをご紹介いただく。
座長:
今泉 和則
(広島大学)
林 由起子
(東京医科大学)
11. 神経鞘腫あるいは脱髄と免疫細胞:病因メカニズムの解明と治療法探索
Schwannoma/demyelination and immune cells: Elucidation of pathogenic mechanism and search for therapeutic strategies
日時 3月28日(日)16:30~18:30
本シンポジウムの主な目的は、神経鞘腫あるいは脱髄のメカニズムを解明するため、神経線維・ミエリンの微小環境に着目し、ミエリンと周囲の免疫細胞との連関による病因メカニズムの解明、および神経鞘腫・脱髄の発生・進行、ならびに関連疼痛の管理を阻害/低減できる治療法を議論することである。シンポジスト1のValerio Magnaghi教授は、神経鞘腫の病因に重要な推定遺伝子、経路、分子標的の同定および免疫細胞応答について、シンポジスト2の三五一憲プロジェクトリーダーは糖尿病による難治性末梢神経疾患治療について、シンポジスト3の山﨑 亮准教授は免疫細胞を介した神経炎症のメカニズム解明と、神経保護を目指した画期的治療法について、シンポジスト4の吉田 成孝教授は髄鞘化と脱髄に関連する細胞外プロテアーゼの機能について、シンポジスト5の神野 尚三教授は中枢神経系の髄鞘と心的外傷後ストレスとの関係について、シンポジスト6の野田は、虚血再灌流後に視神経軸索が脱落するメカニズムと、医療ガス・水素による画期的な予防効果について発表する。外国人招へい研究者と40歳未満ではないものの若手、および女性によるダイバーシティを満たしたシンポジウムである。
座長:
野田 百美
(九州大学)
12. 上皮組織における細胞の環境応答システム
Cellular system for responses against environmental changes in epidermis
日時 3月29日(月)9:00~11:00
上皮組織、特に皮膚は、常に大きな環境変化、病原体や化学物質などに曝されているが、フレキシブルな細胞の応答・制御システムによって組織を維持する精巧な仕組みが備わっている。外部環境の変化に対応するための、膜受容体、及び、細胞小器官による精巧なセンサーとしての役割、それらの情報を周囲に伝達する液性因子などの情報伝達システム、受容した情報に基づき組織を維持するべく変化する細胞の分化・増殖システム、全てが疾患などの現象を理解する上で重要である。これらを広角で捉え、関連を考察することが、基礎研究成果を社会実装するために必須の要件となる。本シンポジウムでは温度変化、物理ダメージ、及び、ウイルス感染による上皮組織による環境変化の受容システムから、変化に対応すべく性質を変化させる細胞や組織の制御システムまでを、多様なバックグラウンドを持つ研究者が集まり議論することで、上皮組織の恒常性維持や再生、さらに新型コロナウイルスに対する治療法への新たな視点を提供したい。
座長:
藤田 郁尚
(株式会社マンダム)
難波 大輔
(東京医科歯科大学)
13. 筋細胞におけるチャネル複合体とその生理的・病態生理的意義
Physiological and pathophysiological importance of ion channel complex in muscle cells
日時 3月29日(月)9:00~11:00
心筋、骨格筋はその収縮機能の効率・力を高める為、特徴的な膜構造を有している。これら膜構造において、そのシグナル伝達の中枢となるのが、様々なイオンチャネル群である。近年の研究では、これらイオンチャネルについて、それ自体の活性化機構だけでなく、その他分子との相互作用を介した複合体形成における重要性が指摘されている。本シンポジウムでは、筋細胞の大きな特徴である興奮収縮連関を司るチャネル複合体形成の重要性と、chronicな筋細胞生理あるいは病態形成を司る興奮転写連関に関与するチャネル複合体の重要性について、最新の知見を5人の講演者により提供いただき、筋細胞の生理・病態生理における今後のチャネル研究展開について議論する。
座長:
冨田 拓郎
(信州大学)
中田 勉
(信州大学)
14. 神経分岐パターンを肉眼解剖学・発生学・生理学から再考する
Reconsider the nerve furcation patterns based on the studies of macroscopic anatomy, embryology, and physiology
日時 3月29日(月)9:00~11:00
本シンポジウムでは, (脊髄)神経分岐パターンについて肉眼解剖学, 発生学, 生理学の手法を用いて得られたこれまでの研究成果を総合的に討論したい. 神経分岐パターンの理解のためには, 以下についての議論が必要と考える。①成体における脊髄神経分岐パターンの詳細な観察(肉眼解剖学), ②筋分化と神経分岐との関係の発生学的な観察, ③神経伸長のメカニズムの分析。これらについて最新の知見を御講演いただき, 神経分岐パターンに関する様々な疑問点を明確にすることで, 脊髄神経の形態学・発生学・生理学を多様な研究角度から討論し理解を深め, 脊髄神経の形態形成を解明することを目的とする。
座長:
影山 幾男
(日本歯科大学)
時田 幸之輔
(埼玉医科大学)
15. 脳発達に対する環境影響:内分泌系の関与
Brain development and environment -The involvement of endocrine system
日時 3月29日(月)14:20~16:20
脳発達と機能的成熟は環境因子により影響を受ける。環境からの影響は内分泌系を介して脳発達へ作用することが多い。その結果,脳の性分化,ストレス応答,概日リズム調節,記憶,行動などに不可逆的な変化をもたらす。また,環境因子による発達期の一過性の内分泌系かく乱の影響は,その後の過程で一旦はキャッチアップされたように見えても,成熟後に様々な疾病として発現する可能性も指摘されており,DOHaD (Developmental Origins of Health and Disease)という概念も一般的に受け入れられるようになってきた。これらの背景のもとに,本シンポジウムでは,それぞれ特徴的な環境刺激を用いて発達期の環境因子による脳発達の変化を解析している若手研究者を招いてシンポジウムを企画した。
座長:
鯉淵 典之
(群馬大学)
小澤 一史
(日本医科大)
16. 口は幸いのもと ~口腔感覚と全身機能のCommon factor~
The mouth is the gate of happiness! -Common factors between Oral Senses and Whole body-
日時 3月29日(月)14:20~16:20
近年、口腔外の器官・組織で発見された機能因子が、口腔内においても重要な機能を担っていることも明らかになっているが、逆に、口腔内で発見された機能因子が口腔外の思わぬ組織で発現している例も多々見受けられ、口腔機能と全身機能とが思わぬ相関を見せることで、互いの研究に幸をもたらすようになってきた。そこで、本シンポジウムでは、医学系、歯学系の立場で活躍するそれぞれ2名のシンポジストを招聘し、口腔内に発現している機能因子が、他組織でも発現している例、あるいは、反対に口腔外に発現している機能因子が口腔内でも重要な機能を担っている例を紹介していただくことで、医学系・歯学系両方の研究者にとって意義のあるシンポジウムを企画した。加えて、シンポジストは医学系、歯学系とも、形態系と機能系の研究者を1名づつとし、本合同大会にふさわしい解剖学と生理学の両面からアプローチできる企画を目指した。
座長:
硲 哲崇
(朝日大学)
熊本 奈都子(
名古屋市立大学)
17. 拡張する睡眠研究―次の10年―
Expanding Sleep Research - The Next Decade-
日時 3月29日(月)14:20~16:20
睡眠は幅広い動物に認められる行動であり、哺乳類ではノンレム睡眠とレム睡眠からなる。ノンレム睡眠を特徴づける睡眠徐波は睡眠要求を反映しているとも考えられている。最近、前障がデルタ波の発生に必須の役割を果たすことが明らかになった。睡眠の機能は明らかではないがシナプス強度の恒常性維持に必要な状態であるという仮説が有力視されている。睡眠覚醒は視床下部を中心とした神経回路によって制御されるが、視床下部には冬眠様状態を誘導するニューロン群が存在することが示された。本シンポジウムでは、生理、解剖のアプローチから、睡眠の制御と機能、さらには冬眠を制御する神経機構について議論する。
座長:
船戸 弘正
(東邦大学)
山中 章弘
(名古屋大学)
18. 電子線によるオルガネライメージングの新たな挑戦
New Approach for Electron Beam-based Organelle-imaging
日時 3月29日(月)14:20~16:20
電子線によるオルガネライメージングは新たな時代へと移行しつつある。近年の走査型電子顕微鏡の装置開発に伴い、広い視野を透過型電子顕微鏡の分解能に近い解像度で解析でき、集束イオンビーム加工観察装置(FIB)と走査型電子顕微鏡(SEM)を組み合わせることにより、生体組織の3次元再構築が可能となった。また、光線-電子線相関顕微鏡法(CLEM)も高精度なin-resin CLEMへと発展しつつある。本シンポジウムでは、電子線を用いた最新の超微形態解析手法・技術による、オルガネラ3Dイメージング、in-resin CLEM、FIB-SEMによる神経細胞の超微形態解析、超微形態3Dブレインマッピングなどについてのトピックスを集め、これからの超微形態イメージングについて議論・展望する。
座長:
谷田 以誠(
順天堂大学)
甲賀 大輔
(旭川医科大学)
19. 分泌学の新展開~形態学と生理学による挑戦
Advances in secretion science - Challenges of morphology and physiology
日時 3月29日(月)16:30~18:30
分泌は、細胞が代謝産物を体腔または体外に排出する現象である。排出された代謝産物は分泌物として標的部位に到達し、生体の防御や恒常性の維持などの生理作用を示す。このような分泌現象を理解するためには、分泌物がどのように分泌されるのかを形態学的な視点で明らかにするとともに、分泌の制御や分泌物の作用を生理学的に解析することが必要である。昨今の新規分泌物の発見や形態観察手法の向上から、これまでの概念とは異なる双方向性の分泌様式なども見い出されており、形態学と生理学の融合から新しい分泌学として理解する必要が生じてきた。そこで本シンポジウムでは、さまざまな切り口から分泌現象を解析する研究者の講演から生体防御や恒常性維持の理解を深めるとともに、新しい分泌学の体系化への足掛かりとなることを目指したい。
座長:
佐藤 貴弘
(久留米大学)
中町 智哉
(富山大学)
20. 解剖学と生理学を基盤としたリンパ学の新展開
New development of Lymphology based on Anatomy and Physiology
日時 3月29日(月)16:30~18:30
近年のリンパ学の急速な発展は生体の循環や免疫の機能調節からがん転移やリンパ浮腫を初めとする様々な病態形成に至るまでリンパ系の生理・病理学的重要性を浮き彫りにし、臨床医学分野ではリンパ系を標的とした新規の治療手段が実現化されるに至っている。第120回解剖・生理学会で催されたシンポジウムでは当時のリンパ学研究の展望が紹介・議論され、大きな反響を呼び、リンパ学における新たな潮流を創り出した。その潮流はその後も留まることなく、医学、生命科学分野から健康科学、創薬・化成品開発の分野にまで大きなうねりをもって拡大を続け、解剖学・生理学と他分野が融合して生み出された新たなコンセプトによるリンパ学が現在繰り広げられている。本シンポジウムでは、未知の領域において挑戦的なリンパ学研究を行っている若手研究者による講演と討論を通して、解剖学・生理学の基盤から社会的貢献性に満ちたリンパ学の明日を開拓する。
座長:
下田 浩
(弘前大学)
河合 佳子
(東北医科薬科大学)
21. Ca2+シグナルの多彩な生理機能細胞内オルガネラから末梢組織、全身まで
Divergent roles of Ca2+ signaling from organelle, cells, tissues to whole body
日時 3月29日(月)16:30~18:30
細胞内Ca2+は、筋収縮、シナプス伝達、遺伝子発現など様々な細胞応答のキー因子である。 これらのシグナルは、これまでは細胞質のBulkのCa2+トランジエントの結果生じると考えられてきたが、近年、細胞内オルガネラ等を介する局所のCa2+上昇が、細胞・組織特異的な機能発現に寄与することが示唆されている。またCa2+シグナルは神経や心臓といった興奮性組織のみならず、幅広い非興奮性の組織においても発生・再生過程などに重要な役割を果たし、さらには全身代謝をも調節するというダイナミックな働きをもつ。本シンポジウムでは、ミトコンドリアにおける局所Ca2+リリースが心筋自動拍動に与える影響、硬組織形成や上皮再生、エネルギー代謝の制御などユニークな最近の知見を発表し、Ca2+シグナルの制御された多様性について討論を行う予定である。
座長:
西谷(中村) 友重(
和歌山県立医科大学)
城戸 瑞穂
(佐賀大学)
22. 皮膚感覚の処理機構とその応用
Cutaneous sensation: Processing mechanisms and their applications
日時 3月30日(火)9:00~11:00
皮膚は外界からの刺激を受け取る最も大きな器官である。皮膚感覚には、痛覚や触圧覚など多様な種類があり、主観的な感覚の性質は個人差が大きい特徴を持つ。本シンポジウムでは、皮膚感覚の基礎メカニズムから応用技術まで取り上げる。痛み情動の生成機序、痒みの神経生理および形態学的特徴、ヒト乳児の触圧覚受容の特性、発達障害者の触知覚、触覚の共有とフィードバック技術に関する知見を紹介する。皮膚感覚における多角的な討議を促し、分野横断型の新しい実験アプローチ創成への貢献を目指したい。
座長:
和田 真
(国立障害者リハビリテーションセンター研究所)
吉田 さちね
(東邦大学)
23. コンチネンス医学の最前線(下部尿路機能障害の病態生理と、その治療法の最前線)
Up-to date of continence medicine
日時 3月30日(火)9:00~11:00
下部尿路機能障害に関連する疾患には、前立腺肥大症、前立腺炎、腹圧性尿失禁、過活動膀胱、低活動膀胱、間質性膀胱炎などが挙げられ、患者はすべての年齢層、男女に及び、病態は多岐にわたり複雑である。治療には、薬物療法に加え、骨盤底筋トレーニング、ボツリヌス毒素注射、仙骨電気刺激等の新たな治療法が確立され、患者の病態に合わせた治療法の選択が可能となった。加えて、排尿自立指導料が保険収載され、他職種が連携して取り組む分野になりつつあり、今後の更なる発展が期待される。
本邦においては、特に排尿生理に関連する基礎研究が、世界に抜きんでて盛んに行われており、「Continence Medicine」の先進国とも言える。本シンポジウムでは、有効な治療がない低活動膀胱、間質性膀胱炎の病態生理に始まり、難治性過活動膀胱の最新治療について専門外の先生にも分りやすく講演する。加えて、尿失禁において重要な部位である骨盤底について、解剖学的知見を述べた後、骨盤底筋トレーニングの意義を講演する。
座長:
相澤 直樹
(獨協医科大学)
宮里 実
(琉球大学)
24. 細胞極性を、形態と機能から探る
Shedding new lights on cell polarity
日時 3月29日(月)14:20~16:20
生体において形は機能を反映し、機能は形に依存し表裏一体である。そのなかで細胞極性は、ニューロンでの情報伝達の方向性や柔軟性、上皮細胞でのバリア機能や物質輸送、受精現象、免疫を例にとるまでもなく、ほとんどの生命現象であまねく重要な基礎となっている。これまでに細胞極性の形成機構と分子の局在の記述の両面で、詳細な理解がなされてきた。本シンポジウムではトピックスとして神経、精子、上皮細胞などを横断的にとりあげ、細胞機能の発現と極性の形成機構についての議論を深める。
座長:
岡村 康司
(大阪大学)
原田 彰宏
(大阪大学)
25. 肝臓の代謝制御とその破綻がもたらす病態
Metabolic regulation in the liver and its pathophysiological consequences
日時 3月30日(火)14:20~16:20
肝臓は糖・脂質代謝を担う生体の代謝恒常性の維持を担う主要な臓器であり、これらの機能破綻は、糖尿病、脂肪肝、肝線維化、非アルコール性脂肪肝炎(NASH)などの疾患を引き起こす。従って、それらの詳細な病態理解と革新的な治療法の確立は喫緊の課題である。近年の研究から、肝細胞の代謝制御は、高脂肪食などの環境変化や種々の免疫系細胞が惹起する慢性炎症などにより種々の影響を受けており、これらの侵襲要因によって正常の調節機構が破綻すると上記のような疾患の発症が誘導されることが明らかになりつつある。本シンポジウムでは、肝臓の代謝研究の現場で世界レベルの研究を展開している6名の若手研究者を演者に迎え、肝臓の代謝制御研究について最新の知見と今後の動向を発信する、魅力的で革新的なシンポジウムとすることを目指す。
座長:
三木 隆司
(千葉大学)
井上 啓
(金沢大学)
26. 体外からの侵害に対する生存戦略
New horizons in crosstalk between nociceptive and self-defense system
日時 3月30日(火)14:20~16:20
生体は常に何かしらの侵害を受けているが、我々には生まれつきそれらに対するさまざまな危機管理システムが備わっている。センサーである侵害受容器を起点とするこのシステムは、複数の生理機能を包括的に調節することを介して生体の恒常性を維持しているが故に、細分化した現代の科学でアプローチすることが難しくなっている。本セッションではこの困難に対し分野横断的な学際研究に挑戦している6名の若手研究者らが、受容器~神経~臓器などの統合システムに関する知見を紹介する。
座長:
丸山 健太
(大阪大学)
高山 靖規
(昭和大学)
27. 心血管の生理応答と病態解明
Cardiovascular physiological response and pathologic analysis
日時 3月30日(火)14:20~16:20
外部刺激、細胞内機能不全、遺伝子異常を含めた体内環境変化は、心血管において多様な生理応答を引き起こす。一方でそれらはすべて、様々な心血管疾患の病因ともなり得る。そのしくみを理解することは、様々な心血管疾患の病因解明と、その治療法の開発に繋がる。本シンポジウムでは、心血管における生理応答や病態生理が、どのような心血管の機能異常とリンクし、最終的に疾患に至るかについてクローズアップする。本シンポジウムでは、特に静水圧や温度環境、咬合障害、血管石灰化、細胞間結合遺伝子の異常などの因子を取り上げ、これらがどのように心血管異常を引き起こすかについて幅広く議論をしたい。
座長:
梅村 将就
(横浜市立大学)
吹田 憲治
(鶴見大学)
28. 大脳皮質局所神経回路構築と学習記憶によるリモデリング
Cortical neural microcircuit and its remodeling during learning
日時 3月30日(火)16:30~18:30
高次脳機能中枢である大脳皮質について、その精緻な神経回路の構築と作動様式に切り込んだ新進気鋭の研究成果を議論することを目標におき、大脳皮質機能の重要な一つの要素である学習機能の基盤神経回路とそのネットワーク再編メカニズムを明らかにする最新の手法に注目した話題を若手の神経科学研究者に提供していただく。生理学と解剖学との融合を基本とした多角的な研究アプローチによる研究成果を統合的に議論し、記憶学習とそれを司る基盤神経回路構築とその再編の実態に迫りたい。
座長:
窪田 芳之
(自然科学研究機構生理学研究所)
古田 貴寛
(大阪大学)
29. 単一軸索の神経生物学:形態と機能
Neurobiology of single axon: structure and function
日時 3月30日(火)16:30~18:30
軸索は神経細胞の出力を担い、脳の精緻な神経回路網を配線する。本シンポジウムでは、単一軸索レベルでの形態解析と機能解析を駆使した最新の研究を紹介し、脳機能のボトムアップ理解の機軸となる中枢軸索研究の現在の到達点を明らかにする。オルガネラレベルでの細胞生物学研究、サブセルラー光生理学と電気生理学、投射解析による細胞種同定、新技術による興奮伝播の直接計測など、斬新で独自な手法に基づく軸索研究の成果を俯瞰し、「単一」軸索の研究でしか得られない、脳の設計図と動作原理の本質的な理解に迫るアプローチの現状と課題、今後の展望について議論する。
座長:
神谷 温之
(北海道大学)
杉原 泉
(東京医科歯科大学)
30. がん幹細胞研究の最前線~分子基盤の解明と新規治療法の創出~
Front in progress on cancer stem cell research -molecular basis and novel therapeutic strategies
日時 3月30日(火)16:30~18:30
がん幹細胞は高腫瘍形成能・自己複製能・多分化能を有する細胞である。がん組織内に潜み、スローな分裂や薬剤排出能亢進などにより治療抵抗性を示し、再発・転移を引き起こすと考えられている。本シンポジウムでは、原発性脳腫瘍である神経膠腫(グリオーマ)のがん幹細胞に焦点をあて、その実態を明らかにすべく多角的視点から議論する。グリオーマの中でもグレードⅣに分類される膠芽腫は5年生存率が7%程度と非常に予後が悪く、その治療標的としてグリオーマ幹細胞が注目を集めている。グリオーマ幹細胞の特異的な生理学的挙動、分子動態、集団特性、ニッチ形成、エピゲノム調節といった側面から研究する研究者が集まり最新の研究成果を紹介する。患者検体由来の細胞株樹立法、グリオーマ幹細胞におけるサブタイプ転換制御、非コードRNAによる遺伝子発現制御、ニッチにおける細胞間相互作用、新規治療法創出など幅広いトピックスを提供する予定である。
座長:
大江 総一
(関西医科大学)
林 美樹夫
(関西医科大学)
31. 生細胞からの計測技術の進歩
Emerging technologies for live-cell imaging and analysis
日時 3月30日(火)16:30~18:30
計測技術の進歩により未知の構造が明らかにされ、また未知の生理現象が明らかにされてきたように、計測技術の創成は形態学、生理学の発展に不可欠である。今日の顕微鏡技術と光技術の発展は生きたままの細胞内の分子の挙動ならびに分子機能・細胞機能の可視化を可能にしてきた。本シンポジウムでは新しい革新的計測技術の開発や生細胞への実際の応用例を複数紹介し、今後の展望についても議論を行う。
座長:
大河内 善史
(大阪大学)
寺田 純雄
(東京医科歯科大学)
32. 心臓研究フロンティア:形態形成・構造から機能まで
Frontiers in heart research: morphogenesis, structure and function
日時 3月30日(火)16:30~18:30
心臓は心室、心房、刺激伝導系といった異なる形態を持った組織が有機的につながって効率よく機能するポンプを形成している。最近の研究から、この分化の仕組みが明らかになっており、調節の破綻が緻密化障害を初めとした種々の異常を引き起こすことが分かってきた。心臓のポンプ機能は個々の心筋細胞が収縮することでもたらされる。収縮にはカルシウムイオン(Ca2+)が必須である。細胞内Ca2+イオン調節は種々のイオンチャネルやポンプ、輸送体によって制御されている。これらは、特殊な接合膜構造を基軸として精緻に制御されており、その破綻が疾患に関連することが明らかになってきた。本シンポジウムでは5人の第一線の研究者に最新のトピックスを提供していただき、心臓構造機能研究の最前線を紹介し、病態の原因や治療戦略の可能性を議論する。本シンポジウムが解剖・生理両学会員の興味を刺激し、今後の共同研究に発展すれば幸いである。
座長:
村山 尚
(順天堂大学)
八代 健太
(京都府立医科大学)
33. 解剖学的・生理学的視点から見た感覚・情動・運動系の機能連関
[生理学女性研究者の会(WPJ)後援シンポジウム]
Functional relationships among the sensation, the emotion and the motion from anatomical and physiological view
日時 3月30日(火)16:30~18:30
このシンポジウムは、感覚系、情動系、運動系という脳の基本的な機能が、どのようなネットワークを形成し環境の変化に対応した行動を起こすかという視点で多角的な討論を喚起することを狙っている。感覚受容のメカニズムや情動系、運動系に焦点をあてたシンポジウムは多いが、それぞれの関連性とネットワークを考える企画はこれまでに無かったものである。今回、5人の講演者により、橋の腕傍核における感覚と自律機能との関連性、炎症による痛みと扁桃体の可塑的変化のメカニズム、感覚-運動の統合領域である前頭皮質での神経回路、感覚情報の大脳基底核を介した運動変換機構、そして、運動が辺縁系を介して痛覚を抑制する機構についてお話し頂く。解剖学会と生理学会の交流と若手の参加も考慮して日本語での発表とする。このシンポジウムは、生理学女性研究者の会(WPJ)の後援により、女性研究者にスポットを当て、女性研究者の活躍を後押しするものである。
座長:
荒田 晶子
(兵庫医科大学)
仙波 恵美子
(大阪行岡医療大学)