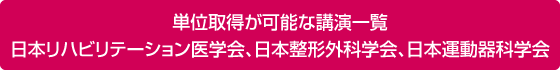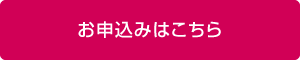単位について
第61回日本リハビリテーション医学会学術集会における各種単位取得は以下のとおりです。
| 現地参加 | WEB参加 (オンデマンド配信視聴) |
|
日本リハビリテーション医学会 |
||
|---|---|---|
| 学術集会参加単位 | 会場で配布する学術集会参加カードの提出により取得可 | いずれかのセッション視聴にて自動的に取得可 |
| 教育研修講演 | 会期中、単位登録受付(セルリアンタワー東急ホテルB2F ボールルームABC)にてお申込みください。事前申込みはありません。 | 7月1日(月)~7月31日(水)に対象のプログラムを受講ください。単位受付は7月1日(月)よりオンラインにて開始します。 |
| 指導医講習会 | ||
| 専門医共通講習会 | ||
日本リハビリテーション医学会以外の単位 |
||
| 日本整形外科学会 教育研修講演 |
本HPからの事前参加登録となります。お申込みはこちらから。 | WEB取得不可
※現地受講でのみ取得できます。 |
| 日本手外科学会 専門医 |
会期中、単位登録受付(セルリアンタワー東急ホテルB2F ボールルームABC) | |
| 日本リウマチ財団 教育研修単位 |
||
| 日本医師会 生涯教育制度学習単位 |
定員に達したため申込を締切ました。 | |
| 健康・体力づくり事業財団 健康運動指導士・ 健康運動実践指導者 登録更新履修単位 |
会期中、単位登録受付(セルリアンタワー東急ホテルB2F ボールルームABC) | |
| 日本運動器学会 運動器リハビリテーションセラピスト 資格継続研修会 |
||
| 日本スポーツ協会 公認スポーツドクター 更新研修 |
||
| 日本骨粗鬆症学会 | ||
| 日本医師会認定産業医研修会 | ||
日本リハビリテーション医学会の単位について
指導医講習会について
日本専門医機構による、専門医制度における指導医研修体制の整備指導に基づく講習会です。受講証明を受けるためには、「①-1」と「①-2」もしくは,「②-1」と「②-2」の2講演を連続して聴講する必要があります。
【現地参加の場合】
- 講習が始まる前に、単位登録受付(セルリアンタワー東急ホテル B2F ボールルームABC)で指導医講習会受講カードを購入してください(2講演:2,000円)。
- 受講カードに必要事項をすべてご記入のうえ、講演終了時に受講した会場の回収箱に提出してください。なお、受講カードを提出しなかった場合は認定されませんのでご注意ください。複数の受講カードを同じ回収箱に提出した場合は、1枚のみが有効となります。
- 受講証明書は各自で保管してください。
- 受講カード・受講証明書の再発行はできませんので、ご了承ください。
| 種別 | 日程 | 時間 | 会場 | 定員 | 講演名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指導医講習会 ①-1 |
6月13日(木) | 15:30~ 16:30 |
第10会場 (渋谷区文化総合センター大和田 6F 伝承ホール) |
240名 | リハビリテーション医学・医療のプロフェッショナルとして心得ておくべきこと |
| 指導医講習会 ①-2 |
16:40~ 17:40 |
高次脳機能障害のリハビリテーション医療 | |||
| 指導医講習会 ②-1 |
6月15日(土) | 16:30~ 17:30 |
240名 | 高次脳機能障害に対する外来診療 | |
| 指導医講習会 ②-2 |
17:40~ 18:40 |
回復期リハビリテーション病棟における指導医の役割 |
※正会員のみ受講受け付けをいたします。日本リハビリテーション医学会以外への受講証明書発行はできませんので、あらかじめご了承ください。
※指導医講習会では、認定臨床医受験資格取得の単位は取得できません。
※1講演のみの受講はできません。
※会期中、先着順により単位登録受付で申し込みを受け付けます。
※定員は、状況に応じ変動する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
【Web参加の場合】
ライブ配信はありません。オンデマンド視聴による単位取得は可能です。
専門医共通講習会について
新専門医制度において、日本専門医機構がすべての基本領域専門医に共通して受講する項目として定めているものに対し、本学術集会が開催するもので、有料講演(1講演1,000円)となります。
医療安全、感染対策、医療倫理は必修講習Aで、専門医更新者全員が更新までに各1回以上受講する必要があります。5つの必修講習Bは、学会専門医から更新した機構認定専門医は2026年度(2026年4月1日)から適用されます。なお専門医共通講習会(必修講習A、必修講習B、任意講習C)の受講単位は、専門医更新に必要な50単位に含めることができますので(5年間で最大10単位まで)、この機会に是非受講してください。詳細は日本専門医機構HPをご確認ください。
【現地参加の場合】
- 講習が始まる前に、単位登録受付(セルリアンタワー東急ホテル B2F ボールルームABC)で専門医共通講習会受講カードを購入してください(1講演:1,000円)。
- 受講カードに必要事項をすべてご記入のうえで、講演終了時に受講した会場の回収箱に提出してください。なお、受講カードを提出しなかった場合は認定されませんのでご注意ください。複数の受講カードを同じ講習の回収箱に提出した場合は、1枚のみが有効となります。
- 受講証明書は各自で保管してください。
- 受講カード・受講証明書の再発行はできませんので、ご了承ください。
| 種別 | 日程 | 時間 | 会場 | 定員 | 講演名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療制度と法律(B) | 6月14日 (金) |
9:50~ 10:50 |
第10会場 (渋谷区文化総合センター大和田 6F 伝承ホール) |
240名 | 医療過誤事件のリスクと対応 |
| 医療倫理(A) | 11:10~ 12:10 |
医療倫理、意識してますか? | |||
| 臨床研究・ 臨床試験(C) |
15:10~ 16:10 |
デジタル技術を活用した研究アウトリーチ活動 | |||
| 医療安全(A) | 16:30~ 17:30 |
医療安全 基本的な考え方とその実践(インシデントレポートの活用) | |||
| 医療福祉制度(B) | 17:50~ 18:50 |
医療福祉制度 | |||
| 感染対策(A) | 6月15日(土) | 11:10~ 12:10 |
第10会場 (渋谷区文化総合センター大和田 6F 伝承ホール) |
240名 | 日常診療における感染対策のキーポイント |
| 地域医療(B) | 15:10~ 16:10 |
百戦錬磨の私から見る地域医療で最も大事なこと | |||
| 両立支援(B) | 6月16日(日) | 11:10~ 12:10 |
第9会場 (渋谷区文化総合センター大和田 4F さくらホール) |
500名 | 治療と就労の両立支援 |
※日本リハビリテーション医学会以外への受講証明書発行はできませんので、あらかじめご了承ください。
※本学術集会では、必修講習Bの医療経済(保健医療等)の開催はございません。
※専門医共通講習会では、認定臨床医、認定臨床医受験資格者の単位は取得できません。
※会期中、先着順により単位登録受付で申し込みを受け付けます。
※定員は、状況に応じ変動する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
【Web参加の場合】
ライブ配信はありません。オンデマンド視聴による単位取得は可能です。
生涯教育研修の単位認定について
本学術集会において取得できる、リハビリテーション科専門医・認定臨床医生涯教育単位は以下のとおりです。
1.学術集会参加:リハビリテーション科専門医2単位、認定臨床医20単位
【現地参加の場合】
当日、学術集会参加カード(ピンク色)を、参加登録受付でお渡しします。
参加カードに必要事項をすべてご記入のうえ、受付に設置予定の回収箱に提出してください。なお、参加カードを提出しなかった場合は単位認定されませんのでご注意ください。参加証明書は、各自で保管してください。
※学術集会参加カード・参加証明書は郵送いたしません。
※学術集会参加カード・参加証明書の再発行はできませんので、あらかじめご了承ください。
【Web参加の場合】
いずれかのセッション視聴後に自動で参加単位が付与されます。
※現地・Web参加による単位は、認定臨床医受験資格者の単位にはなりません。
2.教育研修講演、専門医共通講習会および指導医講習会(リハビリテーション科専門医):1講演 1単位
リハビリテーション科専門医は、基調講演、文化講演、教育講演、共催セミナー(ランチョンセミナー、スポンサードセミナー)、指導医講習会の受講によって、単位(新専門医制度における診療領域別講習)を取得することができます。専門医共通講習会の受講によって、単位(新専門医制度における専門医共通講習)を、取得することができます。あわせて1日で最大7単位、4日間で最大28単位を取得できます。(詳細は「単位取得が可能な講演一覧」をご覧ください。専門医共通講習会および指導医講習会は「指導医講習会について」、「専門医共通講習会について」をご確認ください。)
※現地参加+WEB参加:最大28単位
【現地参加の場合】
- 受講カードは、単位受付で受講前に購入してください。
- 受講カードに必要事項をすべてご記入のうえで、講演終了時に受講した会場の回収箱に提出してください。なお、受講カードを提出しなかった場合は単位認定されないのでご注意ください。複数の受講カードを同じ講習の回収箱に提出した場合は、1枚のみが有効となります。
- 受講証明書は、各自で受講した講演名を記録して保管してください。
- 受講カード・受講証明書の再発行はできませんので、あらかじめご了承ください。
講演の種別によって受講料や受講カードが異なります。下記表でご確認ください。
| 講演種別 | 受講料 | 受講カード |
|---|---|---|
| 基調講演、文化講演、教育講演、共催セミナー(ランチョンセミナー・スポンサードセミナー) | 1,000円/1講演 | 専門医(白色) |
| 専門医共通講習会 | 1,000円/1講演 | 専門医共通講習会受講カード 医療倫理・医療安全・感染対策(緑色) 医療制度と法律・地域医療・医療福祉 制度・両立支援(青色) 臨床研究・臨床試験(紫色) |
| 指導医講習会 | 2,000円/2講演 | 指導医講習会受講カード(灰色) |
【Web参加の場合】
ライブ配信はありません。オンデマンド視聴による単位取得は可能です。
なお、新専門医制度における、日本専門医機構認定専門医としての更新に関しては、日本リハビリテーション医学会ホームページ(「新専門医制度について」の中の「リハビリテーション科専門医更新基準について」)を参照してください。
3.教育研修講演(認定臨床医または認定臨床医受験資格取得):1講演 10単位
日本リハビリテーション医学会認定臨床医、または認定臨床医試験受験を検討中の方は、基調講演、文化講演、教育講演、共催セミナー(ランチョンセミナー、スポンサードセミナー)の受講によって、単位を4日間で最大100単位まで取得することが可能です。1時間(以上)の1講演が連続して2人以上の演者で行われる場合は、すべての演者の講演を聴講した場合に取得できます。
【現地参加の場合】
- 受講カードは、単位受付で受講前に購入してください(1,000円/1講演)。
- 受講カードに必要事項をすべてご記入のうえで、講演終了時に受講した会場の回収箱に提出してください。なお、受講カードを提出しなかった場合は単位認定されないのでご注意ください。複数の受講カードを同じ講演の回収箱に提出した場合は、1枚のみが有効となります。
- 受講証明書は、各自で受講した講演名を記録して申請時まで保管してください。
| 講演種別 | 受講料 | 受講カード |
|---|---|---|
| 基調講演、文化講演、教育講演、共催セミナー(ランチョンセミナー・スポンサードセミナー) | 1,000円/1講演 | 認定医:白色 認定医受験資格取得:オレンジ色 |
【Web参加の場合】
ライブ配信はありません。オンデマンド視聴による単位取得は可能です。
※専門医共通講習会では、認定臨床医、認定臨床医受験資格者の単位は取得できません。
詳細は「単位取得が可能な講演一覧」をご覧ください。
| 注) | 教育研修講演での取得可能単位の最大数は、現地参加、Web参加も同様です。 日本リハビリテーション医学会の単位取得はすべてオンデマンド視聴による単位取得が可能です。 ※日本リハビリテーション医学会以外の単位はオンデマンド視聴による取得はできません。 |
|---|
日本リハビリテーション医学会以外の単位について
本学術集会では、以下の学会・単位の取得が可能です。詳細は各学会・団体のホームページなどでご確認ください。
Ⅰ.教育講演などの受講により単位取得可能な学会・団体について
1.日本整形外科学会 教育研修講演 1講演:1単位(1,000円)
※現地参加でのみ単位取得可能です。
対象の教育講演、共催セミナー(ランチョンセミナー、スポンサードセミナー)は、日本整形外科学会の教育研修講演に認定されています。1時間(以上)の1講演が連続して2人以上の演者で行われる場合は、すべての演者の講演を聴講した場合に1単位取得できます。
学術集会での取得可能単位数の上限は1日で7単位、4日間で最大27単位を取得できます。
詳細は「単位取得が可能な講演一覧」をご覧ください。
お申込みは、オンライン上でのみとなります。
会場で現金でのお申込みは受け付けておりませんのでご了承ください(会期中にオンライン上でお申込みいただくことは可能です)。
<受講証明(専門医対象)>
- ①
- 講演開始10分前から、開始10分後までに日本整形外科学会のICカードまたは仮ICカードを講演会場入口のカードリーダーにかざして、出席登録を行ってください。講演開始10分を過ぎて手続きが完了していない場合、途中退場された場合は、単位取得はできません。
- ②
- 学術集会終了から1週間程度で、日本整形外科学会ホームページの専門医制度取得単位照会システムに反映されますので、ご自身の取得状況を確認できます。
2.日本手外科学会 専門医 1講演:1単位(1,000円)
※現地参加でのみ単位取得可能です。
単位受付にて「受講申込書」に必要事項をご記入のうえ、受講料を添えてお申込みください。受付時に「受講証明書」をお渡ししますので、必要事項をご記入のうえ、講演終了後に「受講証明書(日手会提出用)」を講演会場出口の係員にお渡しください。「受講証明書(受講者控え)」は各自で保管してください。
対象セッションは以下をご確認ください。
| 日程 | 時間 | 会場 | セッション名 | 演題名 | 演者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日 (木) |
18:10~19:10 | 第11会場 | 教育講演20 | 上肢筋の活動特性と筋再教育 | 大山 峰生 |
| 6月14日 (金) |
13:50~14:50 | 第8会場 | 教育講演32 | 筋電図でみえる末梢神経の変性と神経再生 | 蜂須賀明子 |
| 6月15日 (土) |
13:50~14:50 | 第1会場 | 教育講演45 | 関節リウマチに対するリハビリテーション治療のcutting edge | 遠山 将吾 |
3.日本リウマチ財団 教育研修単位 1講演:1単位(1,000円)
(リウマチ財団登録医・リウマチケア看護師・リウマチ財団登録薬剤師・リウマチ財団登録理学・作業療法士)
※現地参加でのみ単位取得可能です。
単位受付にて「受講申込書」に必要事項をご記入のうえ、単位取得証明書料を添えてお申込みください。受付時に単位取得証明書をお渡ししますので、新規登録・更新時まで各自で保管してください。
現地会場にて、参加者名簿に必要事項をご記入のうえ、申込された対象セッションにご参加ください。
単位取得証明書は、受講者名、勤務先を記入して、新規登録・更新時まで保管してください。なお、再発行はいたしません。
登録・更新などの詳細は日本リウマチ財団へお問い合わせください。
対象セッションは以下をご確認ください。
| 日程 | 時間 | 会場 | セッション名 | 演題名 | 演者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月15日 (土) |
13:50~14:50 | 第1会場 | 教育講演45 | 関節リウマチに対するリハビリテーション治療のcutting edge | 遠山 将吾 |
4.日本医師会 生涯教育制度学習単位
日本医師会会員の方は受講内容に応じて、演題ごとに単位・カリキュラムコードの取得が可能です。どの領域を何時間学習されたか申告してください。
<単位とカリキュラムコード>
講演内容に対応した1カリキュラムコードを指定し、各カリキュラムコードの学習時間(単位)を申告してください。
カリキュラムコード(CC)
- 「日本医師会生涯教育カリキュラム<2016>2022年4月版」で定める、学習領域を示す84の項目。
- 講演内容に応じ、受講者自身が演題ごとにCCを決定してください。
例:糖尿病の内容=CC76(糖尿病)
単位
- 学習時間を示すもの。30分=0.5単位とする。
- 1日の上限はありません。挨拶、休憩時間は受講時間には含まれません。
例: 糖尿病の内容の講演を合計3時間受講した=CC76を3単位
<受講を証明するもの>
学術集会の参加証の写しを添付することで申告いただけます。
<申告受付時期>
2025年4月
<申告方法>
- 日本医師会雑誌2025年3月号に同封する申告書に、1年分の申告単位等を記入し、参加証(写しでも可)を添付のうえ、所属の郡市区医師会に提出してください。
詳しくは日本医師会生涯教育online(http://www.med.or.jp/cme/about/index.html)をご確認ください。
5.健康・体力づくり事業財団 健康運動指導士・健康運動実践指導者登録更新履修単位
この第61回日本リハビリテーション医学会学術集会は、健康・体力づくり事業財団健康運動指導士及び健康運動実践指導者の登録更新に必要な履修単位として、講義3.0単位が認められます。(認定番号:246268)
<申込方法>
【現地参加の場合】
参加受付後、「健康運動指導士証および健康運動実践指導者証」を、単位受付にお持ちください。
登録番号を確認のうえ、受講証明書をお渡しいたしますので、申請まで各自で保管してください。また、単位受付にて「登録更新に係る認定講習会受講証明書交付者一覧表」に、登録番号と氏名をご記入のうえ、各セッションにご参加ください。
登録・更新等の詳細は健康・体力づくり事業財団へお問合せください。
【Web参加の場合】
学術集会から3か月以内に、学会の参加証のコピーを含む単位認定に必要書類を健康・体力づくり事業財団へご自身で送付してください。
登録・更新等の詳細は健康・体力づくり事業財団へお問合わせください。
6.日本運動器科学会 運動器リハビリテーションセラピスト資格継続研修会
※現地参加でのみ単位取得可能です。
単位受付にて「受講申込書」に必要事項をご記入のうえ、受講料(1講演/1単位/1,000円)を添えてお申込みください。受付時に受講証明書をお渡ししますので、講演終了後に「セラピスト研修会事務局保存用」を講演会場出口の係員にお渡しください。「受講者保存用」は各自で保管してください。
※「セラピスト研修認定番号(9桁の数字)」が必要となりますので、忘れずにご用意ください。
※受講証明書を、当日中に提出し忘れた場合は無効となりますのでご注意ください。
※単位取得ができるのは、セラピストとして認定されていて、認定証の有効期限があるセラピストのみです。資格取得研修会を受講しただけで、認定証を持っていない方や認定証の有効期限が切れてしまっている方が受講しても単位は取得できません。
対象セッションは「単位取得が可能な講演一覧」をご確認ください。1時間(以上)の1講演が連続して2人以上の演者で行われる場合は、すべての演者の講演を聴講した場合に1単位取得できます。
登録・更新等の詳細は日本運動器学会へお問い合わせください。
7.日本スポーツ協会公認スポーツドクター 更新研修
※現地参加でのみ単位取得可能です。
資格をお持ちの方は、ご自身のスポーツ指導者マイページにて更新研修受講状況をご確認のうえ、手続きをしてください。
更新研修受講終了申請方法
対象セッションを、合計4時間(240分)以上聴講してください。各セッションは、最初から最後まで聴講いただく必要があります。
申込方法
単位受付にて「受講申込書」に必要事項をご記入のうえ、「出席確認カード」を受け取ってください。
「出席確認カード」に必要事項をご記入のうえ、日本スポーツ協会までメールにて送付してください。
(送付期限:2024年7月8日(月))
※その際、ネームカードのコピーを添付してください。
【送付先メールアドレス:drat-kakunin[あ]japan-sports[ど]or[ど]jp([あ] を @ に,[ど] を . に変えてください。)】
対象セッションは以下をご確認ください。
| 日程 | 時間 | 会場 | セッション名 | 演題名 | 演者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日 (木) |
11:20~12:20 | 第6会場 | 教育講演5 | 股関節疾患に対するリハビリテーション治療の意義と注意点 ~術前から術後まで~ |
平尾 昌之 |
| 6月13日 (木) |
18:10~19:10 | 第8会場 | 教育講演14 | パラスポーツ(障がい者スポーツ)におけるメディカルチェックと安全管理 | 牛尾 会 |
| 6月14日 (金) |
8:30~9:30 | 第1会場 | 教育講演21 | アスリートを支える脊椎疾患マネジメント -腰椎分離症と黄色靱帯骨化症について- | 加藤 欽志 |
| 6月14日 (金) |
11:10~12:10 | 第8会場 | 教育講演31 | 体外衝撃波治療事始め基礎知識から臨床応用まで | 見目 智紀 |
| 6月14日 (金) |
11:10~12:10 | 第11会場 | 教育講演38 | 体性感覚機能の可視化と機能向上に向けたアプローチ | 大西 秀明 |
| 6月14日 (金) |
13:50~14:50 | 第11会場 | 教育講演39 | バイオメカニクスから見た下肢関節間トレードオフ | 福井 勉 |
| 6月15日 (土) |
13:50~14:50 | 第8会場 | 教育講演61 | 血友病のリハビリテーション治療:今までとこれから | 田澤 昌之 |
| 6月15日 (土) |
16:30~17:30 | 第1会場 | 教育講演47 | 股関節疾患・手術のリハビリテーション診療 | 神野 哲也 |
| 6月15日 (土) |
17:50~18:50 | 第1会場 | 教育講演48 | 変形性膝関節症 〜その予防に向けての再生医療・医療機器開発〜 | 石川 正和 |
8.日本骨粗鬆症学会(認定番号:240080)
本人の名前の記載された学会参加証(コピー可)を5単位(非基本項目)の骨粗鬆症学会認定医受講証または3単位の骨粗鬆症マネージャー教育研修会受講証として取り扱います。学会参加の証として、認定更新時までPDF保存するなどして、ご自身で保管してください。当日、受講証は配布しません。
また、参加者名簿の記載も不要です。学会参加証のコピーを紛失された場合、単位として認められませんのでご注意ください。
登録・更新等の詳細は日本骨粗鬆症学会へお問い合わせください。
9.日本医師会認定産業医研修会
| 事前参加登録制です。既に定員に達し申込終了しました。 |
日本医師会認定産業医制度における生涯研修会の単位が取得可能です。
対象セッションは以下をご確認ください。
| 日程 | 時間 | 会場 | セッション名 | 演題名 | 演者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日 (木) |
11:20~12:20 | 第8会場 | 教育講演11 | 治療と仕事の両立支援 ~その意義と課題~ |
山徳 雅人 |
| 6月13日 (木) |
15:30~17:30 | 第4会場 | シンポジウム6 | 脳損傷者に対する職業リハビリテーション | 佐伯 覚 渡邉 修 扇 浩幸 |
| 6月14日 (金) |
16:30~18:30 | 第4会場 | シンポジウム18 | アクセシビリティ 〜病院から在宅・職場までシームレスな利用を目指して〜 |
高尾 洋之 細井 裕司 三宅 琢 |
Ⅱ.学術集会への参加、発表などにより単位取得可能な学会・団体について
本単位は、現地参加での単位取得となります。
単位申請については、各学会・団体にご確認のうえ、ご自身で行ってください。(50音順)
日本看護協会 認定看護師自己研鑽ポイント
日本緩和医療学会
日本義肢装具士協会 生涯学習システム単位
日本言語聴覚士協会
日本作業療法士協会
日本小児神経学会
日本神経学会
日本臨床神経生理学会
日本心臓リハビリテーション学会
日本摂食嚥下リハビリテーション学会
日本糖尿病療養指導士認定機構 ※臨床検査技師・理学療法士のみ
日本認知症ケア学会
日本脳卒中学会
日本脈管学会
日本リウマチ学会
日本老年医学会
日本老年精神医学会